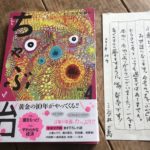「いつもやる気」はありえない。価値の創造と運用のマネージメント。
こないだ大学の後輩でもあるメディアアーティストの市原えつこさんから「独立して二年間経って、独立当初のようなやる気がなくなってきました」という相談がありました。
「独立後の1年間はアドレナリンとやる気が常時出てたけど、だんだん枯渇してきました」というお悩み相談をフリーの大先輩の小倉ヒラクさんにできて良かった?
「やる気がなくて当たり前、やる気がある一瞬のタイミングにいかに周囲を巻き込んでやらざるを得ない状況に自分を追い込むかが大事」とのこと— 市原えつこ / Etsuko Ichihara (@etsuko_ichihara) April 7, 2018
で、僕がその時思ったのは「そもそも常時やる気なんておきない」ということ。「100%内発的なやる気」はレアメタルのような希少資源なので、ゆっくり採掘するのが吉です。
僕の話をするとだな。
僕は自分でもビックリするぐらい「やる気あるタイム」が少ない。たぶん創造的なことをできる時間はよくて15%くらいで、あとはやるべきタスクを消化したり調べものしたり整理整頓したりお昼寝したり。
「なんだその怠け者っぷりは!もっと気合入れて仕事したらどうなんだ?」
という突っ込みも聞こえてきそうですが、僕はやる気タイムの割合を増やす気もなく、考えているのは限られた15%の価値をいかに引き出すか。
思うに、「やる気」ってのはそんなに出ないからこそ価値があるんですよね。
だから「常に100%創造的な自分」を目指すライフハックって「三食全部サーロインステーキ食べる」みたいで胃もたれしそう。「たまに出るやる気」にレバレッジをかけて日々をのらりくらりと暮らすのが結局は長く続くと僕は思います。
やる気を「希少なもの」とカウントするのか「常時あるもの」とカウントするので仕事に対する取り組みが変わってくる。
「希少なもの」としてカウントすると、やる気ないタイムは「希少資源のマネージメント」として割り振られることになります。常に資源を採掘しまくるより、適切な量を採掘してその価値をマネージしたほうが生産性が良い、と言えるのではないかしら?
表現やプロダクトが生まれるのは「やる気ある(創造的)タイム」ですが、その表現やプロダクトの「価値」が生まれるのは「やる気ない(運用)タイム」だったりする。
だからやる気ないタイムはやる気あるタイムと同じく大事なんです。
やる気ない自分は、やる気ある自分のマネージャーの役割。
やる気あるハイテンションな時に「こんなことやりたい!」と用事を仕込んでおいて、やる気がフェードアウトしたタイミングで「やれやれ」と用事を片付けていくバランスで僕の仕事は回っています。ずっとやる気あると片付かない用事がどんどん増えるので、やる気はぼちぼちくらいじゃないと破綻する…!
「いつもやる気100%」って思うほど良いものじゃないと思う次第です。
やる気が低空飛行でもうまく日々の作業を運用する仕組みを設計するのが、モチベーションに左右されずに長く活動を続けるコツなのだなと学びましたです
内発的な動機はナマモノなので
「周囲どころか自分自身すら騙す」というスキルを身につけていきたい— 市原えつこ/ Etsuko Ichihara (@etsuko_ichihara) April 7, 2018