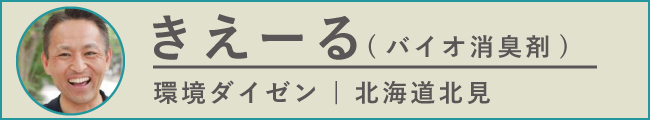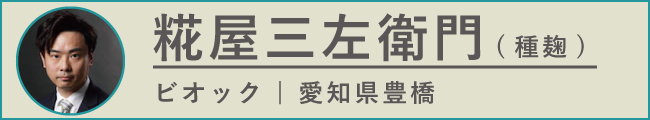しば漬け(京都府大原)| 辻しば漬け本舗
風の吹き抜ける大原の名物漬け物

京都の発酵といえば漬け物。千枚漬けやすぐきも心惹かれるけれど、僕にとっての京つけものといえばやっぱりしば漬け。スーパーで普通に売っている比較的メジャーなものではあるけれど、実は京都のローカリティに根ざした土着な発酵食品なんだね。
しば漬けの起源をたどると、京都市内を北部に登っていった大原地区で伝統的につくられている、赤紫蘇の葉と大原で取れる夏野菜のナス(きゅうりや茗荷を加えることも)と少量の塩で作られる乳酸発酵食品であるとことがわかる。
スーパーで全国流通しているしば漬けは、このシンプルなオリジナルしば漬けに追加で調味料や食材を追加したアレンジレシピで、実は僕はここ大原ではじめて「オリジナルしば漬け」を体験したのだった。
オリジナルしば漬けのポイントをあげるとだな。
・塩分が少なく、主に乳酸発酵によって防腐機能を持たしている
・熟成期間が長い(半年〜一年ほど)
・風通しが良い大原の気候を活かした発酵食品
この結果、比較的味がアッサリして上品、かつ赤紫蘇のピンク色が鮮やかな京らしい雅な漬け物ができあがるんだね。特筆すべきはその香り。フレッシュでフローラルな匂いが赤紫蘇から立ち上ってくる。激しく食欲をそそりつつエレガントなのが京都らしいですなあ。僕のこれまで食べていたしば漬けは何だったのか…
どうやってつくる/食べる?

▶How to 仕込み
A:夏に収穫した赤紫蘇と刻んだナスと塩を混ぜ、樽に漬け込む
B:樽に重しをかぶせ、数ヶ月〜一年ほど熟成させる
☆基本のレシピは赤紫蘇とナスと塩のみ。現在はそこにキュウリや茗荷などを加える
☆基本のレシピでは塩分は10%以下。乳酸発酵によって味をつけていく。
▶食べかた
・お茶請けにポリポリかじる
・お茶漬けにのせる
▶食べられている地域
京都府内(90年代以降より全国)
▶微生物の種類
複数の乳酸菌
旅のメモ

今回お邪魔した辻しば漬け本舗は家族経営のローカルメーカー。
地元でとれた赤紫蘇とナスのみでつくるオリジナルしば漬けの品の良さに感動。
しば漬けのオリジンは、平安時代後期、つまり1000年近く平家の末裔や皇族との関係を持つ由緒正しいもの。中世には大原の山を下って京都市内にしば漬け売りが行商に出かけていたそうです。
赤紫蘇が風に揺れる大原の旅。めちゃ気持ちよかったなあ…

47都道府県の発酵が一堂に会する大展覧会『Fermentation Tourism NIPPON』、今年春4/26〜7/8に開催予定です。47都道府県のうち、36都道府県まで到達。いよいよラストスパート!
Fermentation Tourism NIPPON supported by