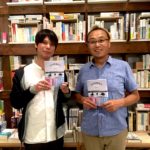閉ざされた島で生きること。
おはようございます、ヒラクです。ようやく暑さが和らいで、日が落ちるのも早くなってきました。
さて。瀬戸内国際芸術祭からもう一つメモ。
瀬戸内海に「大島」という島があります。
国立療養所大島青松園という、ハンセン病患者を収容する施設があり、20世紀の初頭から約90年間、「閉ざされた島」として存在してきました(僕も今回はじめてこの島の存在を知りました)。
ハンセン病に関しての詳細はこちら。国立療養所大島青松園に関しての詳細はこちら。
1960年代には治療法が確立していたのにもかかわらず、それから約40年の間そこに住む人達は隔離されたままでした。で、1996年に「らい予防法」が廃止されたときには、もうみんな高齢者だったわけです。
そんなシリアスな歴史を刻んできた大島。ハンセン病や瀬戸内の歴史に関しての素人のヒラクなりに考えたことを記しておきます。
僕にとって最も衝撃的だったのは、島の景色。
お隣の女木島、男木島なんかと全然違うんですよ。町並みが。
瀬戸内の島の町並みはだいだい、潮風に耐えられるように黒ずんだ杉壁の家が並び、村の人々が自分で積んだであろう石垣に沿って道がくねくねと続いている。風土にあった、漁村のクラシカルな風景なわけです。
対して大島。道も建物もキレイに整備されて、白くて清潔で、のっぺりと個性が無い。人気もなければ、生活感もなく、「公立病院の殺風景な空間が島全体を覆っている」感じなわけです。
僕はこの風景を「住むひとを人間として扱わない」という意識がつくり出したものだと見ました(露骨な言い方をしてすいません、でもそんな感じだったんだもん)。
本当は「ここには人間が住んでいない」と思っているけど、それを露骨に表に出すと政治的に正しくないから、表面上は「清潔な住居」「設備のある診療所」「転んで怪我をしないような整備された道」を用意して突っ込まれないようにしている。
でも。
そこに、ひとが住まうなかで感じるであろう「喜び」に対する想像力はない。全っ然ない。町を設計する前提として、そこに「喜びを享受する」という感性が「無かったこと」にされている。
名古屋造形大学チームがつくったささやかな資料館には、そういう場所においてそれでも「楽しく生きる」ためにつくり出した工夫の跡が残されているわけですが、なおさら町全体の景観とのギャップが悲しくなってくるわけです。
「なんと悲しい場所なのだろう」と胸に刻んで、また自分の街へと帰っていく…
というのがまあテンプレートの反応だと思うんですが、じゃあその自分の街を改めて客観的に思い返してみたらどうかというと、これまた驚愕なわけですよ。
『道も建物もキレイに整備されて、白くて清潔で、のっぺりと個性が無い。』
おお、日本中のニュータウンや地方都市、郊外で見かける景色ではないか。
表面には広告や看板やネオンのデコレーションが施されているけれど、それを外してみたら…
「生きる喜び」を自分で作り出せない場所に住む人は、働いてお金を稼いで、「喜びをもたらすガジェット」を買うほかない。
ではもし、ノーマルな労働者としての生産力を失ってしまったら?
きれいに消毒された無機質な空間で、ただ息をして死ぬのを待つ。
僕は別に、大島だけの話をしているわけじゃない。
「じゃあどこの話をしているの?」