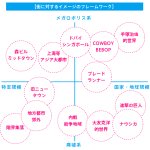映画「100年ごはん」に抱いた違和感。映画における「主体」とは何か?
ジャーナリズムでもなく、作者の表現でもないドキュメンタリーとは何か。
それってつまり、プロパガンダ映画でないか?
こないだ映画「100年ごはん」上映イベントでのゲストとして大林千茱萸監督とお話ししてきました。その時に感じた違和感を、改めてブログにまとめておきます。
行政施策としてのドキュメンタリー
この「100年ごはん」は、大分県臼杵市の有機農業に関わる行政職員や生産者たちの取り組みを追ったドキュメンタリー。堆肥づくりからはじめて、地元の子どもたちに食べさせる給食を有機食材にするまでの道のりを取材しながら、「100年のスパンで食と農業のことを捉え直す」という、題材自体はしごくまっとうなもの。→詳しくは公式サイトで
なんだけど、とにかく引っかかるシーンが多い。「あれ?ナレーターが読み上げる台詞が行政文書みたいだぞ?」とか「地元テレビの報道の引用多すぎやしないか?」とかね。
監督の話を聞くに、この映画は自治体と制作会社の合同出資で制作されたもの。つまり、自治体がスポンサーの「公共事業としての映画」という要素を多分に含んでいる。
体裁としては普通のドキュメンタリーとして撮られているんだけど、ディテールが行政施策っぽい。そこに違和感を感じるんですね。
例えば、地元の農家を紹介するナレーションで「◯◯さんは、こうおっしゃっています」と読み上げるシーンがある。この「おっしゃる」という表現は、クライアントに対してのもの。ジャーナリズムとしてのドキュメンタリーであれば「◯◯さんはこう言っています」でいいはずだ。
表現において「中立」とは何か?
「おいおいヒラクくん、揚げ足取りみたいなマネはやめろよ。みんな楽しんで見ていたじゃないか」
うん、まあそうなんだけどさ。でもここには僕にとって見逃せない問題があるのだぜ。
上映後のトークで、「どうしてこういう手法で撮ったんですか?」と監督に聞いてみたらば「作者のメッセージを押し付けたり、慣行農業を批判するわけではなく、見る人それぞれに自分なりの考えや感想を持ってほしかった」「特定の主役をつくるのではなく、群像劇にしたかった」という論旨の答えでした。
※慣行農業:化学肥料や農薬などを使用する戦後スタンダードになった農業のこと
これはいっけん「思慮深い発言」に思えるが、果たしてそうだろうか?
以下ポイントを2点に絞って考えてみる。
▶群像劇の意味は何か
特定の主人公を採用しないということは、そこにいる様々な立場が対等に扱われるということで、ロシアアヴァンギャルドの古典「戦艦ポチョムキン」のような方法論だ。しかし気になるのが「慣行農業をやっている農家」や「有機農業を否定する人」がほとんど登場しない点(確か一人登場していたか)。自治体の有機農業推進施策の枠組みの外側にいる人は「群衆」から弾かれているように見えてしまうであるよ(一般的には多数派なはずなんだけど)。そういう意味で、監督の言う中立性はこの「群像劇」という方法論では担保されないと僕は感じる。
▶人それぞれの感想を持てるかどうか
もしこれを本気で思っているとしたら、映画を見て「別に有機農業じゃなくていいんでないか」という感想も許容しなければいけないはずだ。なんだけど、↑の有機農業推進施策の枠組みの外側にあるものがほとんど映画に登場しないので、「やっぱ、有機農業っていいよね」という感想になってしまう(政策が始まる前はどうなっていたのか状況がもっと説明されていればよかったのかも)。
「素材を並べときます。和食でもフレンチでも中華でも、後はみなさんが調理してください」
と言いつつも、その素材がパクチーやナンプラーや青唐辛子みたいなのがズラッと並んでいたとしたら「まあ…タイ料理つくるしかないか」となる。「しょうがないよね。この料理教室、タイ文化推進センター主催だし」というがこの「100年ごはん」の図式だとヒラクは思うのですが。
作者の主体を消したら、スポンサーの意向が残る?
僕はデザイナーなので、仕事にクライアント=スポンサーが関わることがたくさんある。なので、別に「PR映画はダメだ」という話をしたいわけじゃない。
ドキュメンタリーの体裁の「プロパガンダ映画」だとしたら微妙だよね、という話だ。
もう一つだけ映画から具体例を挙げる。
有機農業推進施策が進んでいく様子に「私たちは、ゆっくりとですが一歩一歩進んでいます」というようなナレーションがかぶさるシーンがある。
この「進んでいる」というのは、「ある理想に向かって前進している」という意味だと思われるので、多分にメッセージ性の強い言葉だ。
しかしこれは「作者=監督からのメッセージではない」ということらしい(ゲストトークで僕はそう理解した)。では誰からのメッセージかというと、2つの可能性が思い浮かぶ。
・有機農業推進をしている自治体からのメッセージ
・人類が必然的にたどり着くであろう真理からのメッセージ
前者だとするとクライアントのPRということだからまあ納得できる。もしかしたら後者の可能性が残っているかもしれないが、そうだとすると大変だ。「有機農業推進」が「クジラ漁廃絶活動」みたいなファナティックな様相を帯びてしまうからだ。
わざわざ僕が言うまでもないが、有機農業は別に唯一の真理ではない。ある特定のグループが優先的に選択している農業の方法論の一つだ。それがもし多くの人に役立つようであれば、暫定的に色んな人が取り入れる、というプラクティカルな話だと僕は思っている。
「100年ごはん」について僕が持つ違和感を整理してみるならば「群像劇」や「作者の主体を消す」という方法論を取り入れて、普遍的な映画作品に寄せることで「有機農業という真理を布教するプロパガンダ映画」のように見えてしまう、ということだ(実際に制作側がどう思っているかに関わらず)。
画面の端々から見えるディテールや素材の選択がそういう「メタメッセージ」を送ってしまっているのだ。
直球のPR映画、あるいは臼杵市の取り組みに監督が個人として共感して表現した作品としてなら、僕は困惑せずにこの映画を見ることができた。
しかし僕は「プロパガンダ映画」として見てしまったために、「味噌汁のダシもゆっくりとれない忙しない自分」を断罪されている気持ちになってしまったのであるよ。
以上、ヒラクによる感想でした。ドキュメンタリーって難しいねえ。
【追記:長いから読みたい人だけどうぞ】
サルトルの「自由への道」という小説がある。特定の主人公を採用しない群像劇形式で、かつサルトル自身が作者としての神の視点を持たずに「さも登場人物が自分自身で意思決定をしている」体裁で物語が進行していく(作者が文中で自問自答したりするし)。
ここでサルトルは「全てをジャッジする神の視点」を捨て、人間の運命はそれぞれの主体に委ねられている、という事を表現したかったわけですが、しかしそこには落とし穴があった。「みんなが主体的に考えたら、まあ正解に気づくよね」という先入観があったわけさ。
「西洋の唯物論的な世界観が、未だ啓蒙されていないアルジェリアはじめ第三世界が必然的にたどり着くゴール&正解であり、それをこっちから上から目線で言うのも何だから、自分で考えてもらってたどり着いてほしいよね、というのがつまりサルトルさんの言いたいことなんだね?」
という問いを提出したのが、僕の心の師、レヴィ=ストロース御大。
なにか究極的な「正解」が用意されている、という意味で、結局神の視点は残っているわけだ。しかし、レヴィ=ストロース御大が解明したのは「人間社会において、優劣や正解は存在」しないということであり、同時に「全ての人間が、もれなく自分の属している文化的フレームの中にいる偏向した存在」であるということだった。
「歴史は必然的に進歩し、人間は必然的に正解を選ぶ」という発想自体が「そういうモードのフレーム」として「第三世界の啓蒙されてない文明のフレーム」と同様に「偏向的」なのであるよ。
僕が信じる知性とは「自分が偏向的であることに対しての自覚ができる」ことで、その視点はレヴィ=ストロース御大から授かった(という意味で、僕の思想自体もレヴィ=ストロース的に偏向しているのだけどね)。